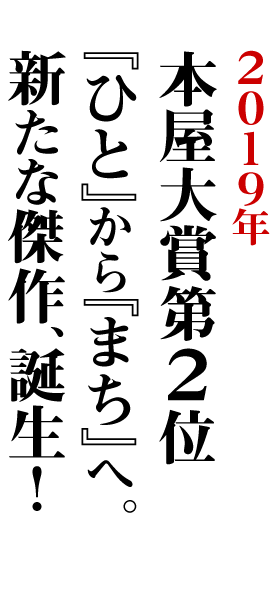



身をもって教えてくれたこと。
あらすじ
尾瀬
ヶ
原
が広がる群馬県
利根
郡
片
品
村で
歩荷
をしていた祖父に育てられた
江藤
瞬一
。
高校卒業とともに上京し、引越の日雇いバイトをしながら荒川沿いのアパートに住んで四年になる。
かつて故郷で宿屋を営んでいた両親は小学三年生のときに火事で亡くなった。
二人の死は、自分のせいではないかという思いがずっと消えずにいる。
近頃は仕事終わりにバイト仲間と他愛のない話をしたり、お隣の母子に頼まれて虫退治をしたり、町の人々に馴染みつつあった。そんなある日、突然祖父が東京にやって来ると言い……。
ひとがつながり
まちができる。
僕にもうひとつ、
帰る場所ができた。
人と交わり、
強く優しく成長していく若者の物語。
画/田中海帆

こんな時代に必要な、そっと野に咲く花のような、素朴で美しい物語。
じいちゃんの真っすぐな想いは、瞬一に受け継がれて、その温かさが周りの人達に伝わり、『ひと』と『まち』に血が通いだす。
うさぎや 矢板店 山田恵理子さん私のなかでは、『ひと』のさらに上を行く傑作だ。
100キロもの荷物を山小屋へ運ぶ、歩荷で生計を立ててきた紀介じいちゃんが、魅力的過ぎて目が離せない。心に温かな灯がともる作品です
文真堂書店 ビバモール本庄店 山本智子さん淡々と日々の生活を書いているだけなのに、どうしてこんなに心を動かされるのか。驚かされます!!
精文館書店 本店 保母明子さん今の世の中、とても難しい。けれど、この小説の言葉たちが、ポンと優しく背を押してくれる気がしました。
伊吉書院 盛岡南サンサ店 土屋静香さん朴訥な祖父の優しさや力強さ、たまに発する言葉の深さに何度も涙が滲んできました。生きることに慣れない人間に、大切なことを教わったような気がします。
未来屋書店 大日店 石坂華月さんひたむきに、そして強く生きる青年に「がんばれ!」とつい叫びたくなります。
本の王国グループ 宮地友則さん染み入るような、いい小説を読んだなと心から思える作品でした。
瞬一の実直さが、ひととしてごく当たり前の、あるべき道へ導いてくれるようなニュートラルな視点を取り戻す作用のある本だと思いました。ときわ書房 千城台店 片山恭子さん大きな出来事がなくてもひとは成長できる、無理しなくても自然体で生きていてもいいんだよと言ってもらえているようで心があたたかくなりました。
また『ひと』とのリンクがまるで古い知人に会えたような気がして嬉しかったです。水嶋書房 くずはモール店 井上恵さん何より、『まち』を読むだけで、とても心が温かくなりました。こんなに温かくなるなら、この冬にぴったり。
それから、砂町銀座が出てきて、ニヤリ。そして惣菜の田野倉が出てきてニヤリ。精文館書店 豊明店 近藤綾子さん
著者コメント

Profile
千葉県生まれ。2006年「裏へ走り蹴り込め」でオール讀物新人賞、08年「ROCKER」でポプラ社小説大賞優秀賞を、そして2019年に『ひと』で本屋大賞第2位を受賞。著書に『ホケツ!』『家族のシナリオ』(小社刊)『みつばの郵便屋さん』『ひりつく夜の音』『近いはずの人』『リカバリー』『本日も教官なり』『それ自体が奇跡』『夜の側に立つ』『ライフ』『縁』などがある。

村と町とじいちゃんと瞬一
一月一日 片品村 江藤家
「うまいよ。じいちゃんが焼いてくれた餅を食べると、正月だなって感じがする。今年も、これを楽しみに帰ってきたよ」
「餅ぐらい、いくらでも焼いてやる。瞬一は、休め」
「うん。一年分休むよ」
「引越の仕事は、どうだ?」
「コンビニよりは、僕に合ってるかな。歩荷に近い感じがするよ」
「そうか。東京でも、荷運びはできるか」
「荷物はどこにでもあるからね。じいちゃん、昔言ったじゃない。重い物を持つことには慣れないって。あれ、少しわかったような気がするよ」
「じいちゃんが、そんなこと言ったか」
「ほら、僕がまだ中学生で、初めて歩荷の手伝いをさせてもらったとき」
「あぁ。言ったかもな」
「あのときはほんとに重かった。やってみたいなんて言うんじゃなかったと思ったよ」
「瞬一」
「ん?」
「尾瀬はお前を好いてくれてた。東京も、たぶん、好いてくれる」
「そうなれば、いいけどね」
「そうなるよ。じいちゃんにはわかる。村も町も、瞬一のことは好きだ。東京に戻っても、こっちに帰ってきたときみたいに、ただいまを言え」
「そうするよ」
「餅、もう一個食え」
小野寺史宜の既刊本
-
サッカー部引退を間近に控えた高校三年生の宮島大地は一度も公式戦に出場したことがない。だが、母を亡くしてから同居している絹子伯母さんには「レギュラー」と嘘をついていた。最後の大会が終わったら進路を決めなければならない。悩む大地に十二年前に家を出た実父から突然、連絡があり……。家族、仲間、将来──迷いながら自分だけのポジションを探し出す物語。
-
元女優の母、元叔父さんの父、反抗期の妹、そしてヒッチコック好きのぼく。訳ありそうに見えるけれど、ぼくら安井家は平穏で普通のはずだった。それなのにある夜、母が突然、ぼくらの知らない男の人を看とると宣言した瞬間、歯車が狂い始める。母の恩人だというその(・・)人(・)に、ぼくは会いに行く決意をしたけれど……。揺れ動く家族と少年の心を瑞々しく描ききる、成長の物語。
-
2019年本屋大賞第2位。柏木聖輔は20歳の秋、たった一人になった。女手ひとつで東京の私大に進ませてくれた母が急死したのだ。大学は中退。仕事を探さなければと思いつつ、動き出せない日々が続いた。そんなある日、空腹に負けて吸い寄せられた惣菜屋で、買おうとしていた最後に残った50円のコロッケを見知らぬお婆さんに譲った。それが運命を変えるとも知らずに……。
-
両親を亡くし、尾瀬の荷運び・歩荷を営む祖父に育てられた江藤瞬一は、後を継ぎたいと相談した高三の春、意外にも「東京に出ろ」と諭された。よその世界を知れ。知って、人と交われ――。それから四年、瞬一は荒川沿いのアパートに暮らし、隣人と助け合い、バイト仲間と苦楽を共にしていた。そんなある日、祖父が突然東京にやってきて……。孤独な青年が強く優しく成長していく物語。
-
社会人三年目の三上傑には、大学生の妹、若緒がいた。仲は特に良くも悪くもなく、普通。しかし最近、傑は妹のことばかり気にかけている。傑の友だちであり若緒の恋人でもある城山大河が、ドライブデート中に事故を起こしたのだ。後遺症で、若緒は左足を引きずるようになってしまった。以来、家族ぐるみの付き合いだった大河を巡って、三上家はどこかぎくしゃくしている。教員の父は大河に一定の理解を示すが、納得いかない母は突っかかり、喧嘩が絶えない。ハンデを追いながら、若緒は就活に苦戦中。家族に、友に、どう接すればいいのか。思い悩む傑は……。






